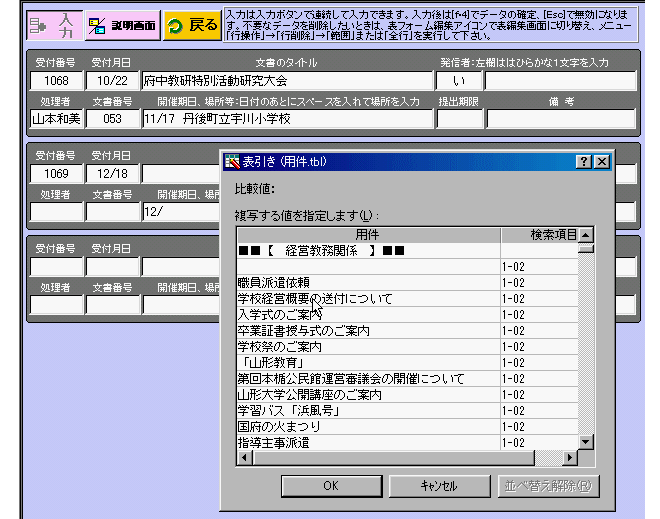[研修2] コンピュータを利用した文書管理 〜統合事務処理へのシステム〜
2-1 エクセルを使った文書の収発
2-2 文書管理(山形)
2-3 事務処理(岩手)
2-4 文書管理(駒田)
[研修3] 機能的な研修体制 〜今後の研究、及び研修システム〜
3-1 教育活動支援システム
3-2 岩手の統合システム
3-3 ソフト供給体制
3-4 アフターフォロー体制
3-5 共同開発体制
[研修2] コンピュータを利用した文書管理 〜統合事務処理へのシステム〜
今年で6年目を迎えたコンピュータ研修会は、初年度から一貫して「教育活動支援システム」を取り上げてきました。当初から学校内に在る様々な事務処理を有機的に結合することを狙いとしていましたが、初めの頃は旅費請求事務のOA化の視点に重点が置かれていました。
その中で、旅行実績の多くが出張依頼文書に基づいて行われていることに気付くことになり、そしてそれは文書収受事務という事務処理によって、事前に把握されているデータであることに気付くこととなりました。用務内容や出張先のデータは文書収受の時点で既に入手できているのです。そのデータをそのまま旅費請求の処理に使えないかというのが、次への課題となってきていました。
ここでは、文書事務で得られたデータを有効的に活用する工夫の事例から、統合的な事務処理システムについての可能性について見ていきます。
2-1 エクセルを使った文書の収発
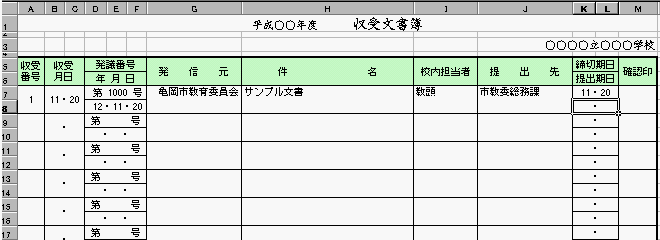
- これはエクセルで作られた文書収受のフォームです。このようなフォームは、表計算ソフトだけでなく、以前からワープロ等でも作られて来ているのではないでしょうか。
- 学校現場での運営はまだまだ文書によって行われることが基本となっています。出張は出張依頼文書に基づいて行われますし、様々な報告も、提出依頼文書によって成される事が多いでしょう。そんな時、文書の収受データをコンピュータに入力しておくだけでも、並べ替え・検索等には威力を発揮するのではないでしょうか。
2-2 文書管理(山形)
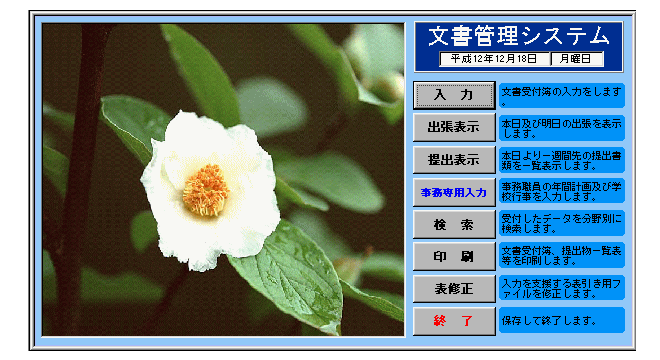
- これは入力や検索の方法に工夫を凝らした山形県酒田市で利用されている文書管理システムの例です。入力されているデータを並べ替えたり検索することを重要な目的として作成されていますので、データベースシステムを使って作成されています。
ホームページアドレス → http://www.ic-net.or.jp/home/tttyyy/kiriv7.html
- 文書収受の事務処理においては、入力しなけければならないデータの多くは、以前から何度も入力している定型的なデータであることが多いですから、それらの文字をあらかじめコンピュータに登録しておき、必要に応じて呼び出し、一覧から選ぶという工夫が随所に見られます。
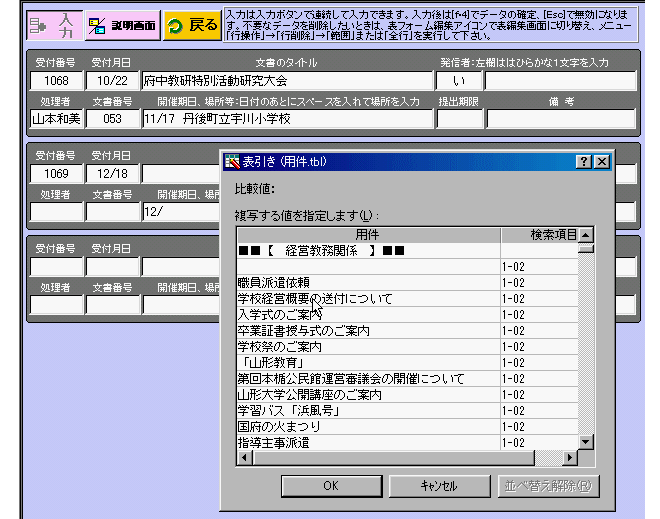
- これらの工夫によって、単に表計算フォームやワープロに入力しておいたデータを活用することと比べればはるかに機能的な活用が可能となっています。また、より適切に活用しようとするとそれぞれのソフトを十分に使いこなす必要がありますが、メニューから選択するだけで実行できるという工夫は、ソフトの操作方法に不慣れでも利用できることを意味し、特に初心者にとっては丁寧な工夫と言えると思います。
- 作った自分だけが使うというなら自分さえわかっていれば良いような作り方でも良いでしょうが、せっかくのシステムですから、他の人にも使ってもらえるほうが望ましいと思います。何人かで使ってみると、もっと良いアイデアも出るでしょうし、もっと適切な工夫を思い付くこともあるでしょうから。それを考えれば、メニュー方式などの丁寧な作り方は必要不可欠となってくるのではないでしょうか。
- 現在の表計算ソフトでは、入力するときの工夫の可能性については、データベースソフトと比べたときには弱いと言わざるを得ないのではないかと思います。その辺りの課題が、酒田市で表計算ソフトではなくデータベースソフトが使われている理由かもしれません。
2-3 事務処理(岩手)
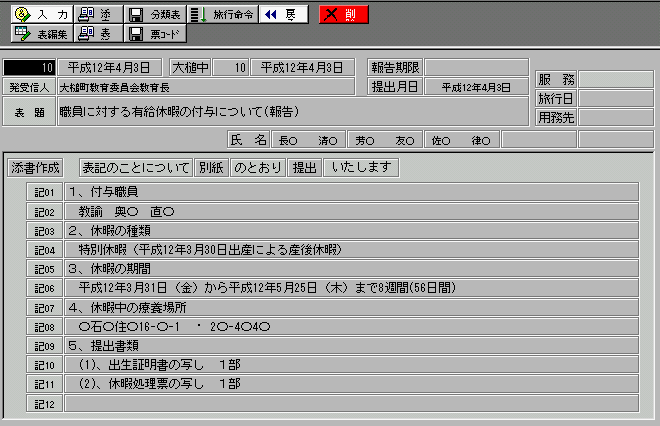
- これも同じくデータベースシステムを使った文書管理システムの事例です。画面を見てもわかるように、収受された文書の管理だけでなく、作成された文書の管理をも視野に入れた作りとなっています。
ホームページアドレス → http://www14.freeweb.ne.jp/school/yo-chiba/
- コンピュータによる文書管理のシステムは今までからもたくさんありました。文書収受簿が必要とされているように、文書発送簿の必要性も認められており、収受とともに発送の部分もコンピュータに管理させようとするシステムもあったように思います。しかし、その途中経過である、文書の処理の流れまでを監視するという部分については見過ごされて来たのではないでしょうか。
- 今、ペーパーレスオフィスというものが提唱されて久しくなり、IT革命とも言われている中で、文書の一連の流れのOA化を見るとき、このような発想は今後重要な部分になるのかもしれません。
- 事例のシステムの鑑文書の自動作成機能は、収受された文書がどのように処理されていくのかという流れを管理することができるという可能性に繋がるのではないかと思います。これは、収受や発送や、文書作成、決済など、それぞれの単位事務をひとつの流れの中に統合するということを意味します。お互いに関連付けると言い換えてもいいかもしれません。単位事務がシステム化された次の課題は、相互の連携なのです。
2-4 文書管理(駒田)
- 今まで見てきたデータベースによる文書管理の事例は、いずれも「桐Ver8」という市販データベースソフトで開発されたものです。
- このコンピュータ研修会で一貫して取り上げられてきた教育活動支援システムもまた、おなじ桐によって開発されたアプリケーションソフトですが、Windows用ソフトである「桐Ver8」ではなく、Dos用の「桐Ver5」での開発となっています。
- 当初、学校に整備されてきたコンピュータがDosをOSとするコンピュータであったため桐Ver5を使った開発となったものですが、一昨年来からの各校でのハード整備の流れを見てみると、WindowsをOSとするハードのみの整備となっていますので、今後はWindowsベースでの利用を念頭に置いた取り組みを進めて行かざるを得ないことは明白です。
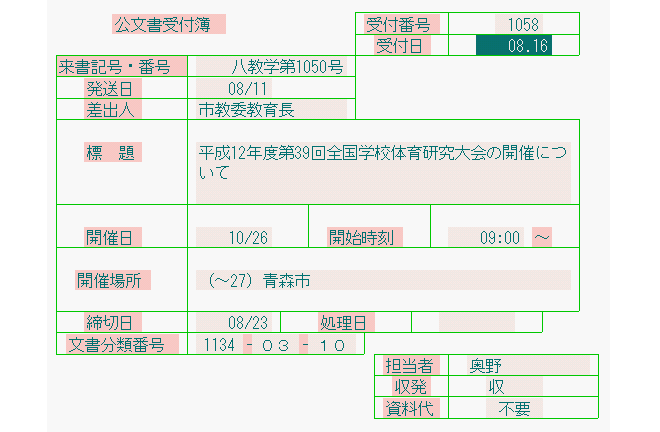
- 最近になって公開されたソフトは全てがWindows用と言ってもいいほどですが、この事例もWindows版の桐Ver8を使ったアプリケーションです。文書の収受を中心としたシステムですが、文書発送も視野に入れた開発がなされています。今後は収受データを元にした旅費支給システムへの応用へと発展する可能性が大きいシステムです。 → [ダウンロード実行]
- Windows用のソフトとDos用のソフトを見比べたとき、もっとも大きな違いは情報の表示量ではないでしょうか。あるデータを画面に表示させようとしたときの表現力の差は歴然としたものがあり、Dosベースで動いている限りは不可能なような表現に対する要求でも、Windowsベースの場合は、それが可能です。例えば、入力時にいくつかの候補を表示させ、その中から選択して入力する、などという工夫はWindowsだからこそ可能だとも言えます。
- 今後、データの共有を基本とする統合事務処理システムを考えていく上では、ヘルプ機能の充実などが大きなウェイトを占めていくものと思われますが、その際には、このWindowsの豊かな表現力が力を発揮するのではないでしょうか。
- コンピュータを使って学校事務を効率的・機能的に処理していこうとしたとき、コンピュータの能力を十二分に活用するためには統合事務処理という考え方を進めていく必要がありますが、同時にそれは、操作方法が複雑化するというマイナス面も持つものとなります。このマイナス面をカバーしてくれるものとしてのWindowsの表現力に期待したいと思っています。
※※ 「学校事務の研究会グループ」で一緒に情報の交換をしませんか? ※※
有志が集まって、学校事務に関するいろんな話を、ワイワイガヤガヤと交換しています。
色んな話でも盛り上がっていますし、仕事に対する疑問や悩みも出ていますよ。
この研修会の内容についてもう少し聞いてみたいなと思われたら、
是非、研究会に参加してみてください。
詳しくは、こちらを ----> [学校事務の研究会]