  |
| 〜 コ ン ピ ュ ー タ 研 修 会 〜 |
12.11.20 於)亀岡市国際センター
※12.11.20 亀岡市国際センターにおいて12年度コンピュータ研修会が開催されました。
ここでは研修会の内容に沿って資料の再提示と研修内容の概要について解説します。
但し、一度に全てを報告することは作業的に困難なため、順次報告という形になりますのでご承知おきください。
また、内容については、あくまでも全て沼田の個人的な見解ですので、合わせてご了解下さい。
[研修1] 文書様式集の有効的な活用 〜電子データの効率的な整理・活用法〜
1-1 学校事務便利帳
1-2 給与関係質疑応答集
1-3 ファイルのツリー配置
1-4 ハイパーテキストによる「学校事務の手引き」
[研修2] コンピュータを利用した文書管理 〜統合事務処理へのシステム〜
2-1 エクセルを使った文書の収発
2-2 文書管理(山形)
2-3 事務処理(岩手)
2-4 文書管理(駒田)
[研修3] 機能的な研修体制 〜今後の研究、及び研修システム〜
3-1 教育活動支援システム
3-2 岩手の統合システム
3-3 ソフト供給体制
3-4 アフターフォロー体制
3-5 共同開発体制
[研修1] 文書様式集の有効的な活用 〜電子データの効率的な整理・活用法〜
ここでは文書の様式等に代表される電子データの有効な整理と活用の方法について考えていきます。
ワープロで様々な様式を作った時、それは電子データとして捉えることが出来ます。
同様の電子データは、例えば「給与の手引き」であったり、「事例集」であったり、「法令集」であったりします。
それらは独立したファイルとして保存されている場合もあるでしょうし、1つのファイルに整理・統合されている場合もあるかもしれません。
それらのファイルは、時として膨大な量となることも十分に考えられる中で、機能的で、且つ合理的な活用の方法を工夫することは、もはや必然と言えるのではないでしょうか。
ここではその方法のいくつかについて、具体的な事例を見ていく中からより望ましいあり方を考えていきます。
1-1 学校事務便利帳
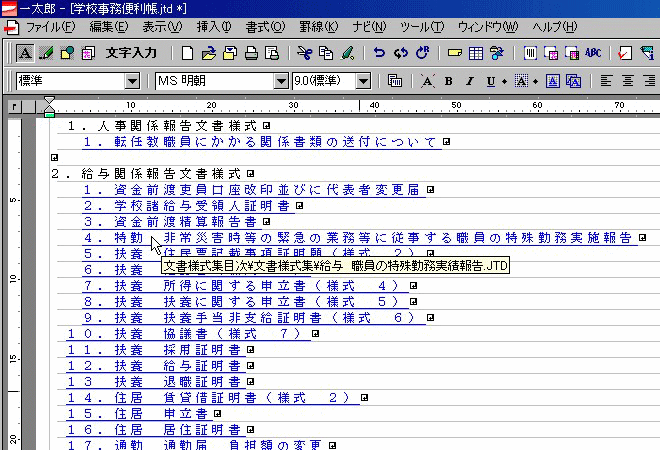
- 学校事務便利帳は、各支部、又は個人で作成されてきた文書様式等のファイルを効率良く呼び出すための工夫として作成されています。
- 一般に、様式などのファイルは特定のフォルダに数多く作成され、いざファイルを利用しようとした時、目的のファイルを探し出しにくい状況も出てきているのではないかと思われます。
- これは一太郎V10からサポートされているハイパーリンクを文書中に挿入し、目的のファイルを関連付けたものです。利用しようとする者はこの目次ファイルから目的の項目を選択し、クリックすることによってファイルを呼び出すことが出来ます。もちろん呼び出されたファイルは一太郎の文書ですから、必要な修正を加えた後、印刷することで活用することが出来ます。
- 学校事務便利帳はダウンロードして利用することが出来ます。
ダウンロードファイルは自己解凍型圧縮ファイルとして提供されますので、適当な親フォルダに保存し、実行ファイル(benricho.exe)をダブルクリックしてください。下部に必要なフォルダを作成し、解凍されます。→[ダウンロード実行]
- <課題点>
学校事務便利帳は一太郎V9以降のバージョンでのみ利用可能であり、V8においては機能拡張を行うことによって利用可能です。
しかし、一太郎そのものの起動にも時間を要するため、軽快に作業を進めるには不向きとも考えられます。
1-2 給与関係質疑応答集
- インターネットの普及によりWebサイト閲覧の機会が多くなるにつれ、ハイパーリンクの有用性については十分に認められているものと考えられます。
今や、ハイパーリンク機能をサポートしているアプリケーションソフトは一太郎に限らず、エクセルやアクセスを初めとするマイクロソフト社のソフト群を初めとして多くのソフトに上っています。
ここではハイパーリンク機能の代表的な利用法として、Webサイトでの具体的な利用法を見ていきます。
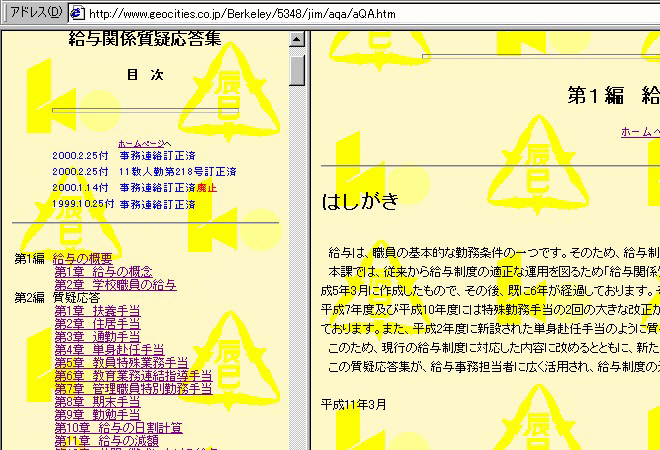
- Webサイト「給与事務質疑応答集」は東京都江東区辰巳小学校市川先生の個人HPです。
ホームページアドレス:http://www.geocities.co.jp/Berkeley/5348/jim/aqa/aQA.htm
- このサイトでは一つの画面を目次と本文の2つのフレームに分け、左フレームで全体を見ながら本文を右フレームに表示させるという手法を取り入れています。
- 一太郎で開くファイルを選択するときなど、プレビュー表示をさせながらファイル内容を確認する機能がありますが、ちょうどそれと同じように内容を右フレームに表示させながら左フレームの一覧から選択する、等の使い方に威力を発揮する使い方ではないでしょうか。
- また、Webページとして作成されたものはInternet
Explorer等のブラウザで閲覧することが出来るため、ほとんど全てのコンピュータで見ることが出来ます。一太郎V10が使えないため利用することが出来ない等の問題が起こることがないということも、メリットとして考えて良いのではないでしょうか。
- 尚、このサイトは非常に膨大な量となっていますので、目次フレームの中で効率的に目的の項目を検索する方法の必要性が指摘されています。
例えば、リスト機能の挿入等の工夫を今後検討することが出来れば、より利用しやすいサイトになるのではないかと考えられます。
1-3 ファイルのツリー配置
- 1つのファイルのような電子データであれば、それを効率的に探し出すための工夫として、次のようなことを考えても良いのではないでしょうか。
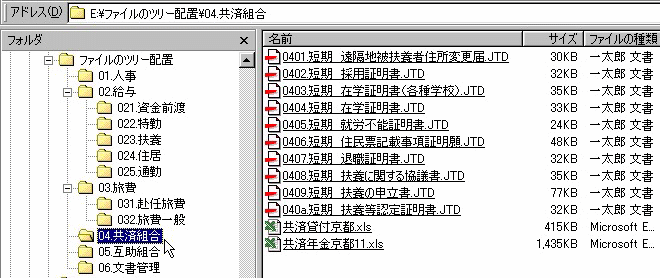
- これは「学校事務便利帳」の各ファイルを適当なフォルダに仕分けしただけのものです。
- 通常、エクスプローラー等を使ってファイルを表示させ、その一覧から目的のファイルを選択するという方法が採られていますが、フォルダの作成を工夫することによって「目次」の役割を果たさせることが可能です。
- またこれは、先ほどのWebサイトでのフレーム割りのように、左画面に項目を表示させ、右画面に内容を表示させるような使い方に似せることが出来ます。
使っているソフトは違いますが、似たようなユーザーインターフェースが作れることも、Windowsの大きな特徴です。
- 学校事務便利帳の各ファイルをフォルダに再整理したものはダウンロードして見てみるが出来ます。
ダウンロードファイルは自己解凍型圧縮ファイルとして提供されますので、適当な親フォルダに保存し、実行ファイル(benricho_1.exe)をダブルクリックしてください。下部に必要なフォルダを作成し、解凍されます。→[ダウンロード実行]
- 尚、この事例では「学校事務便利帳」の各ファイルだけでなく、エクセルのファイル等、関連するファイルも同じフォルダに整理しています。
- かつては、一太郎のデータは一太郎の下部フォルダに、エクセルのデータはエクセルの下部フォルダに、等の仕分け方が多かった時期もありました。データの内容ではなくて、どんなアプリケーションソフトで作られているデータなのかが優先されていた訳です。
- しかし、Windowsの特徴の一つに「ファイルの関連づけ」という機能があります。
付けられている拡張子によって自動的にアプリケーションが起動するという機能です。
例えば、拡張子が「JTD」であるファイルを選択すれば自動的に一太郎が起動し、目的のファイルを表示してくれる、というものです。
- これによって、予め一太郎なりエクセルなりのアプリケーションを起動しておいてからファイルを呼び出すという作業が必要ではなくなりました。
フォルダ内の目的のファイルを選択すれば、必要なソフトは自動で起動されるため、かつてのソフト別にファイルを整理していた方法から、目的別に整理する方法に切り替えることが容易となったのです。
- これも一つの電子データの整理方法と言えるのではないでしょうか。
1-4 ハイパーテキストによる「学校事務の手引き」
- 文書にハイパーリンクを設定する事によって、関連する情報を有機的に結合させる手法は、その文書の情報の量を飛躍的に向上させます。
- 次に、もう一つのハイパーリンクの具体的な活用法を見ていただきます。
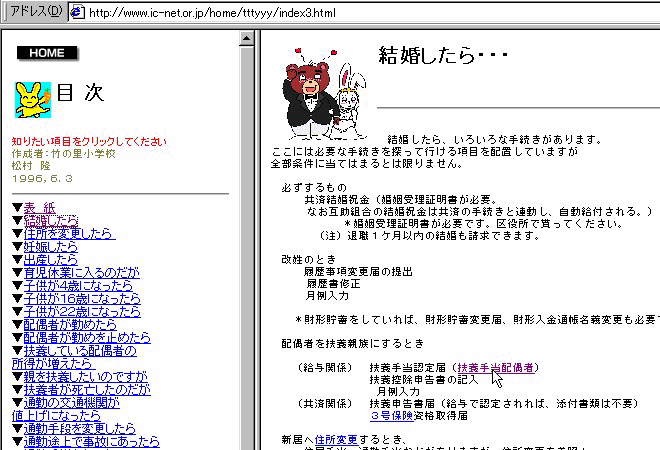
- この事例も「給与事務質疑応答集」と同様のWebサイトでのハイパーリンクの使用例です。
ホームページアドレス:http://www.ic-net.or.jp/home/tttyyy/index3.html
- 前の事例が主として法令関係であったのに対して、このサイトでは具体的な事例毎にまとめられています。
さらに、本文中にも関連する項目に対するハイパーリンクがふんだんに設定されています。
- ある事例に対して調べてみようとした利用者が本文中に設定されているリンクを次々にたどって行くことによって、より知識を深めていけるように工夫されているのです。
- 言い換えれば、多くの電子データを相互にハイパーリンクで繋ぐことによって、それぞれがそれぞれを補完するように働かせることが出来る、とも言えるのではないでしょうか。
- 今後、電子データの活用は、作成者が作成者だけのために利用するのではなく、それを必要とする多くの人たちから利用されるようになってくるのではないかと思っています。
Aさんが作ってくれたファイルは、BさんもCさんも、その他多くの人たちからも利用されるようになるのではないでしょうか。近年、LANの整備が進んでいますが、それらの状況から考えても、そのように感じられます。
- そして、そのための工夫は、ほんの少しのアイデアではないかと思います。
- 今、求められていることは、そんな工夫の交流ではないでしょうか。
※※ 「学校事務の研究会グループ」で一緒に情報の交換をしませんか? ※※
有志が集まって、学校事務に関するいろんな話を、ワイワイガヤガヤと交換しています。
色んな話でも盛り上がっていますし、仕事に対する疑問や悩みも出ていますよ。
この研修会の内容についてもう少し聞いてみたいなと思われたら、
是非、研究会に参加してみてください。
詳しくは、こちらを ----> [学校事務の研究会]

